受付時間 9:00~17:30 / 定休日 土日・祝日
TEL.0246-27-9110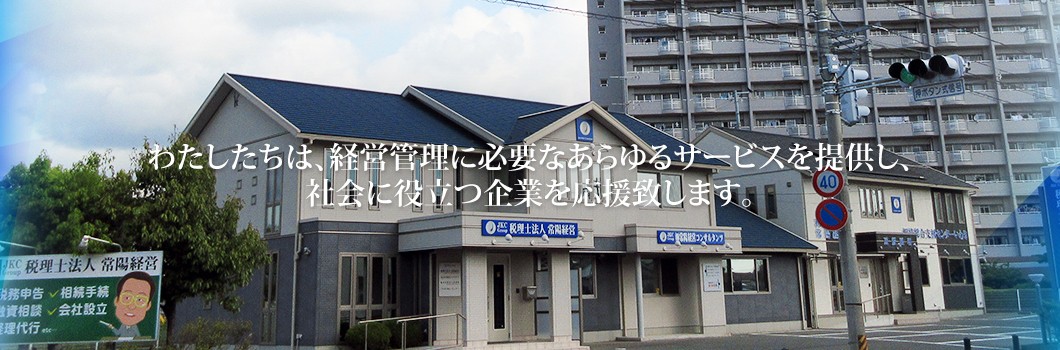
Blog
ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
オリンピックが近づき、各スポーツのニュースが多くみられるようになりました。
福島県のみならず全国各地での盛り上げていきたいものです。
今回から2回に分けて認知症になったらどうなるか、事前の対策についてお伝えします。
厚生労働省によると、国内の認知症患者は年々増加傾向にあります。
現行民法上、認知症を患った人は、「意思能力のない者」として、基本的にすべての法律行為に
制限がかかります。
そこで、患者に代わって財産の処分や運用をするために活用されているのが、成年後見制度です。
制度には「任意後見」と「法定後見」の2種類があり、任意後見制度はあらかじめ患者が任意に
選んだ者を後見人とします。
これに対して法定後見制度は、家庭裁判所が選んだ親族の他、弁護士や司法書士といった専門家が
後見人になります。認知症を患ってからは、自分で後見人を選ぶ判断能力がないため、法定後見
制度しか利用できないことになります。
ここで問題になるのは、法定後見人はあくまで患者本人の財産等を守ることを目的としている
ため、患者の家族のためのお金の移動や、経営者であれば会社のための相続対策ができない点
です。
法定後見人による資産管理が周囲の者にとって大きな足かせになるケースも少なくありません。
ある会社の例では、会長が脳梗塞で倒れ、認知症の診断を受けました。
入院する会長の財産を管理するための法定後見人に弁護士が選ばれ、会長のキャッシュカードや
通帳はもちろん、土地の権利書、会社の貸し付けたお金の借用書や会社の決算書など、ありとあら
ゆるものを弁護士に引き渡しました。ただ、この中には家族の日常の雑費なども含まれていました。
法定後見人は患者本人の財産を守る決まりとなっているため、家族はこれまでの生活水準を維持
することができなくなってしまいました。
判断能力が亡くなった人の財産を悪意のある第三者から守るための制度が、周囲を不幸にしてしま
う結果になることもあります。
そうならないためにも認知症になる前の準備が得策になります。
次回は、事前の対策についてお伝えします。
TEL.0246-27-9110
受付時間 9:00~17:30 / 定休日 土日・祝日